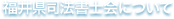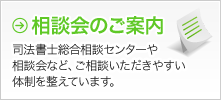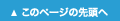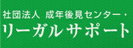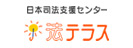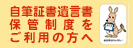後見人に関する事
高齢者・障害者の財産管理(成年後見制度)に関する業務を承っています。
- ひとり暮らしの老後を安心して暮らしたい
- 障害を持つ子供の将来が心配
- 寝たきりの父の不動産を売却して入院費に充てたい
成年後見制度について
認知症等判断能力がないか若しくは不十分のため、不動産の売買や遺産分割協議、銀行預貯金の管理、または身のまわりの世話のために介護サービスや施設への入所に関する契約を結ぶ必要があっても、自分でこれらの契約を締結するのが難しい場合があります。また、自分に不利な内容であっても、十分に判断できないまま契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭う恐れもあります。
成年後見とは一定の手続で選任された成年後見人等が本人を代理して契約等の法律行為を行ったりあるいは本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり本人が後見人等の同意を得ないでした不利益な法律行為を後見人が取り消したりすることによって、本人を保護・支援する制度です。
成年後見制度には大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度について
認知症等により現に判断能力がないか若しくは不十分な状態にある人に対して、申立により家庭裁判所が本人の判断能力の程度に従って後見人・保佐人・補助人等を選任して、本人を援助する制度です。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度によって次のように区分されます。
(1)…本人の判断能力がまったくない場合 「後見」
(2)…本人の判断能力が著しく不十分な場合「補佐」
(3)…本人の判断能力が不十分な場合 「補助」
任意後見制度について
本人の十分な判断能力があるうちに、将来自身の判断能力が衰えた場合に備えて、あらかじめ自らが選任した任意後見人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)をしておきます。これにより、本人の判断能力が衰えた後に、任意後見人は任意後見契約で定められた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」のもと、本人の意思に沿った適切な保護・支援を行うことができます。なお、任意後見契約は必ず公証人の作成する公正証書で締結しておく必要があります。
後見手続きの申立人
申立人は、本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人、任意後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人等、市区町村長、検察官です。
四親等内の親族とは主に、親、祖父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥、姪、おじ、おば、いとこ、配偶者の親・子・兄弟姉妹の人たちになります。
後見人の選任について
後見人等として選任されるのは親族に限定されているわけでもありません。
家庭裁判所は成年後見人等の選任にあたり、(1)本人の心身の状態並びに生活及び財産状況、(2)成年後見人等候補者の職業・経歴、(3)成年後見人等候補者と本人の利害関係、(4)本人の意見等をふまえて総合的に判断します。そのため、弁護士や司法書士、社会福祉士等の法律・福祉の専門家や、それらの公益法人が選ばれる場合もあります。この場合、これらの成年後見人等に対する報酬は、家庭裁判所が決定し、本人の財産の中から支払われることになります。
後見人の仕事は?
成年後見人は本人に代わって、その生活・医療・介護・福祉等の様々な契約を結んだり、財産全体をきちんと管理して、本人が日常生活に困らないように保護・支援します。成年後見人は、その事務について家庭裁判所に報告する等して、家庭裁判所の監督をうけることになります。
しかし、成年後見人の職務は本人の財産管理や契約等の法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護等の身上看護は含まれていません。